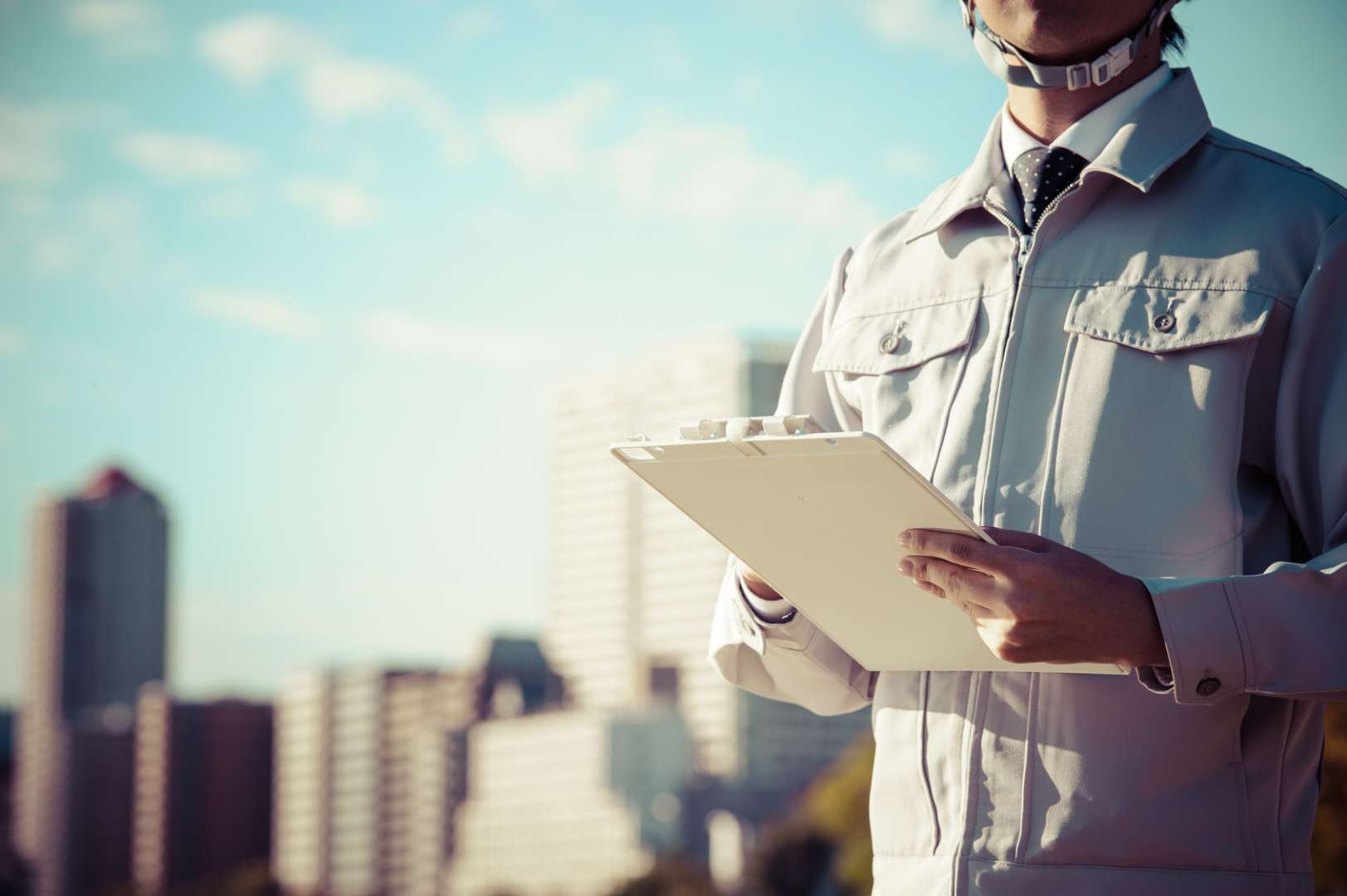ゴムチップ舗装は、柔らかくすべりにくいという特徴から、公園や園庭、歩道などさまざまな場所で使われています。見た目にもカラフルで明るく、安全性とデザイン性を両立できる点が評価されており、特に子どもや高齢者が利用する場所では選ばれることが多くなっています。
雨が降ってもすぐに水がたまりにくく、ぬれてもすべりにくいので、通行する人にとっても安心です。さらに、打ち付けるような足音も抑えられるため、周囲への音の配慮が必要な住宅地や学校などにも適しています。
こうした特性から、近年では校庭の一部舗装や、施設のアプローチ部分、商業施設の通路などにも採用が広がっています。素材としての信頼性に加え、メンテナンスのしやすさや施工期間の短さも、導入が進む理由のひとつです。
施工の基本手順(下地処理〜仕上げまで)
ゴムチップ舗装の施工は、大きく分けて「下地づくり」「材料の混合」「塗り付け・仕上げ」という3つの工程で進められます。まず重要なのが下地の処理です。表面にでこぼこや割れ、段差があると仕上がりにムラが出やすくなるため、既存の地面をしっかりと平らに整える必要があります。コンクリートやアスファルトなど、下地の状態に応じて補修や清掃も行います。
次に、ゴムチップと専用の接着剤(バインダー)を混ぜる工程です。この作業は施工現場で行うのが一般的で、気温や湿度を見ながら最適な比率で調整されます。手早く作業を進めないと硬化が始まってしまうため、ここでは職人の経験が問われます。
混合した材料は、一定の厚みを保ちながらコテなどで均等に塗り広げていきます。塗り付けた後は、ローラーなどで圧着して表面をならし、仕上げます。乾燥にはおおよそ1日程度を要し、完全に固まるまでは歩行を控える必要があります。気温や施工面積によっても時間は前後しますが、施工から使用開始までは比較的短期間で済むのが特徴です。
施工に使われる材料と道具
ゴムチップ舗装に使用される主な材料は、細かく砕かれたゴム粒と、それを固めるための接着剤(バインダー)です。ゴム粒には再生ゴムを用いることが多く、環境負荷を抑えた舗装材としても注目されています。また、使用するゴムの色や粒の大きさによって、仕上がりの印象も大きく変わります。
バインダーには主にポリウレタン系の素材が使われます。透明または薄い茶色の液体で、ゴム粒をしっかり固めながらも弾力を損なわないよう配合されています。この接着剤の品質や混ぜる比率は、舗装の耐久性に直結するため、慎重に管理されます。
道具については、まず混合用の撹拌機、次に舗装面へ材料を運ぶバケットやスコップ、そして塗り付けに使うコテやヘラが必要です。塗布後の圧着にはローラーを使用することが多く、表面をできるだけ均一に仕上げる工夫が求められます。
施工現場では、気温や湿度の変化によって硬化スピードが変わるため、作業スピードと精度の両立が重要です。扱う材料や道具は一見シンプルに見えますが、均質で美しい仕上がりにするには、経験に基づく判断力が求められます。
自分で施工する場合の注意点と限界
ゴムチップ舗装はホームセンターや通販でも材料が手に入るようになり、最近では「DIYでやってみたい」という声も増えています。小さな花壇まわりやベランダの一部など、狭い範囲であれば、自分で施工することも不可能ではありません。ただし、いくつかの注意点を理解したうえで取り組む必要があります。
まず、ゴムチップとバインダーの混合比率は非常に重要です。多すぎても少なすぎても、硬化不良やひび割れの原因になります。また、混ぜる際のスピードや手際が悪いと、硬化が始まってしまい、きれいに仕上がらなくなることもあります。施工中の温度や湿度によっても、乾き具合や接着力が左右されるため、経験のない方にとっては予想以上に難易度が高い作業です。
さらに、表面を均一に仕上げるためには、塗り方や押さえ方にコツが必要です。わずかな段差やムラがあった場合、それが水たまりやはがれの原因になることがあります。広範囲や歩行頻度の高い場所でのDIY施工は、結果的に手直しや再施工の手間が発生するリスクも高くなります。
コストを抑えたいという気持ちは自然なことですが、安全性や耐久性を考えると、プロに任せたほうが長い目で見て安心です。特に公共性の高い場所や小さな子どもが使う場所では、専門的な施工が求められる場面が多いと言えるでしょう。
施工不良を防ぐためのチェックポイント
施工不良を防ぐには、まず下地の状態を正しく確認することが第一歩です。表面にひび割れや油分が残っていないか、十分に乾燥しているかなど、下地処理の段階での見落としは、施工後に大きなトラブルを招く要因になります。また、ゴムチップとバインダーを混ぜる際の時間や配合比率にも注意が必要です。硬化が始まるまでの短い時間の中で、むらなく混ぜる作業は、想像以上に神経を使います。
施工中は、気温が高すぎても低すぎても、材料の硬化や作業のしやすさに影響を与えます。特に夏場や冬場などは、施工に適した時間帯を選ぶことが肝心です。また、風が強い日や湿度の高い日には、仕上がりに影響が出る可能性があるため、天候を見ながらスケジュールを組むことも忘れてはいけません。
仕上げの段階では、表面の厚みや均一性、端部の処理も重要なポイントです。仕上がりに段差や凹凸があると、水がたまって滑りやすくなったり、経年劣化が早まる原因になります。端部の処理が甘いと、そこからめくれやすくなり、補修の頻度が増える結果になります。
これらの工程すべてにおいて、「ただ施工する」だけでなく、「どう使われるか」を想定した判断と技術が求められます。だからこそ、施工を任せる相手選びもまた、大切なチェック項目の一つです。
→ ゴムチップ舗装のプロによる施工事例はこちら:https://www.yurikougyou.jp/construction
失敗しないための業者選びのコツ
ゴムチップ舗装を検討するうえで、信頼できる業者をどう選ぶかは大きなポイントになります。まず確認したいのは、「どのような施工実績があるか」です。公園や園庭、施設の通路など、実際に使われている場面の施工例を提示できるかどうかで、その会社の経験値がおおよそ見えてきます。
また、現地調査をしっかり行い、使い方や利用者の年齢層まで踏まえた提案ができるかも重要です。「ただ舗装する」だけでなく、「安全に長く使えるか」を見据えたアドバイスがあるかどうかで、施工の質に差が出ます。見積もりの内容も、「材料費・施工費・養生など」が明確に分かれて記載されているかを確認しましょう。
もし比較する時間があれば、2~3社から話を聞いてみるのも良い方法です。担当者の説明の仕方や、こちらの話をきちんと聞いてくれるかどうかも、判断材料のひとつになります。費用だけで選ばず、「誰に任せるか」で後悔のない選択をしていただきたいところです。
→ お見積もり・ご相談はこちら:https://www.yurikougyou.jp/contact