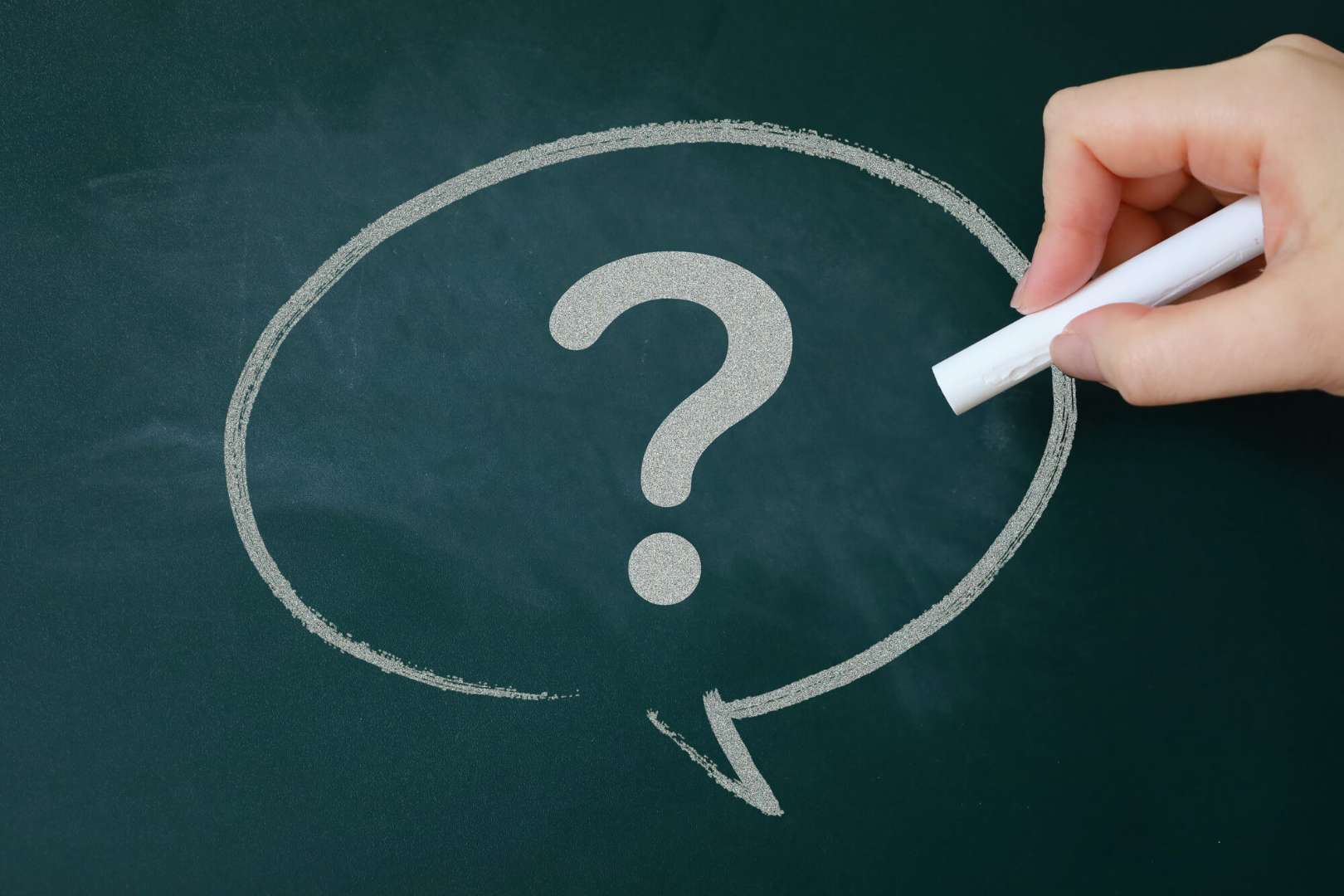子どもたちが毎日走り回る校庭は、思い切り体を動かせる場所であると同時に、転倒や衝突などのリスクと隣り合わせの空間でもあります。そうした中で、けがを少しでも減らし、安全性を高める方法として注目されているのが「ゴムチップ舗装」です。
ゴムチップは、地面の表面に弾力性のある素材を敷くことで、転んだときの衝撃を和らげたり、すべりにくさを確保したりといった効果が期待できます。土のようにでこぼこになることも少なく、雨上がりでもぬかるまずに使えるのも大きな利点です。
全国的にも、保育園や小学校の園庭・校庭での採用が広がっており、土や芝と並ぶ選択肢として定着しつつあります。子どもたちの安全を守るという視点に加え、維持管理のしやすさや見た目の明るさといった面でも評価されています。
子どもの安全を守るための効果とは
校庭でゴムチップ舗装を導入する一番の理由は、なんといっても「転倒時の衝撃をやわらげる」という安全面の効果です。子どもたちは予想もつかない動きをするものです。全力で走っていて転んだとき、硬いアスファルトや乾いた土の地面では、手やひざに大きなけがをしてしまうこともあります。ゴムチップ舗装であれば、表面に弾力があるため衝撃を吸収し、けがの程度を軽減することができます。
また、表面の摩擦係数が高く、すべりにくいのも特徴です。雨が降った後でもすべりにくく、乾きも早いため、雨上がりの校庭遊びも安心して行えます。特に走り回る遊びが多い低学年の子どもにとっては、大きな安心材料となります。
さらに、カラフルな配色が可能なので、校庭全体が明るくなり、活動が楽しくなるという効果も見逃せません。ラインを入れて運動エリアを分けたり、模様をつけて遊び場としての工夫を凝らしたりすることも可能です。
このように、ゴムチップ舗装は子どものけがのリスクを下げながら、活動の場を広げるための安心な選択肢として活用されています。
土や芝生との違い(耐久性・使い勝手)
校庭の地面としては、昔から使われている「土」、手入れの行き届いた「芝生」、そして近年注目されている「ゴムチップ舗装」の3つが主な選択肢です。それぞれに長所と短所がありますが、耐久性や使いやすさの面では、ゴムチップ舗装が優れている点も多くあります。
まず、土のグラウンドは雨が降るとぬかるみやすく、乾くと砂ぼこりが舞いやすいという欠点があります。風が強い日や長雨の後は、使用を控えなければならないこともあり、管理面でも苦労が多いです。一方芝生は見た目が美しく、クッション性にも優れていますが、芝刈りや水やりなど手入れの手間がかかり、維持費用も安くありません。
ゴムチップ舗装はその中間のような存在で、ぬかるまず、乾きも早く、かつ定期的な芝刈りも不要です。落ち葉の清掃や軽い洗浄を行えば、衛生的な状態を保つことができます。加えて、表面が傷んできた場合には部分的な補修も可能なため、全体を張り替えずに済む点もメリットです。
耐久性の面では、使用頻度や気候条件にもよりますが、適切な施工とメンテナンスを行えば10年以上使い続けることも可能です。結果として、初期費用はかかるものの、長期的にはコストと手間のバランスがとれた選択肢といえるでしょう。
ゴムチップ舗装にかかる費用と維持管理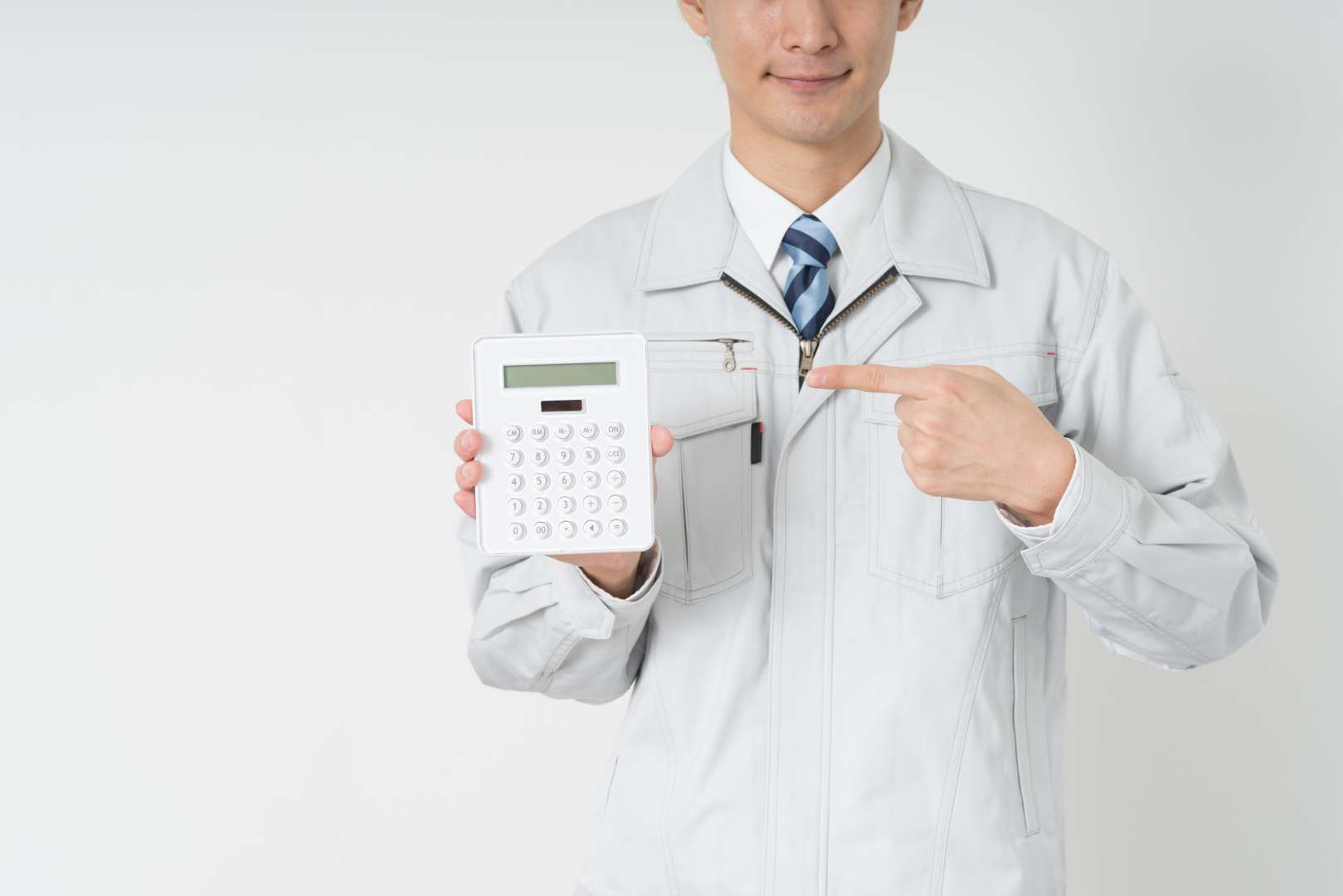
校庭にゴムチップ舗装を導入する際、気になるのが費用面です。一般的に、ゴムチップ舗装は1㎡あたり1万5千円から2万円程度が目安とされており、土やアスファルトに比べると初期費用はやや高めです。施工の範囲が広くなるほど、もちろん全体費用も増えるため、導入前には面積の確認と予算のすり合わせが欠かせません。
ただし、維持管理のしやすさをふまえると、長期的にはコストパフォーマンスの良い選択とも言えます。土のようにでこぼこを直す必要もなく、芝生のように定期的な刈り取りや水やりも不要です。日常的な清掃は、落ち葉や砂ぼこりをほうきやブロワーで取り除くだけで十分対応できます。
また、耐久性があるため、10年を超えて使われているケースも珍しくありません。摩耗やはがれが発生したとしても、部分的な補修が可能であり、全面張り替えの必要がないことも費用面での安心材料になります。
保守的な立場で考えるなら、「安全性」と「手入れの負担軽減」の2つを両立できることが、導入を検討する理由になります。仮に全面施工が難しい場合でも、遊具周辺や転倒リスクの高い箇所だけを優先して部分導入することもできるため、状況に応じた柔軟な計画が立てられます。
実際の施工時に気をつけたいポイント
ゴムチップ舗装を校庭に導入する場合、施工そのものだけでなく、その前後の計画がとても重要です。まず確認すべきなのは、「どの場所を舗装するか」という点です。全体を一気に工事するのが理想ですが、予算や利用状況によっては、利用頻度の高いエリアや、転倒のリスクがある遊具周辺などから優先的に施工する方法もあります。
施工時期についても配慮が必要です。ゴムチップ舗装は天候の影響を受けやすいため、梅雨時期や寒冷期は避けた方が安心です。気温や湿度によって硬化時間が変わるため、予定どおりに進まない場合もあります。行事との兼ね合いや子どもたちの動線も踏まえ、無理のないスケジュールを立てることが求められます。
また、施工後の養生期間も考慮しましょう。舗装が乾くまでには1~2日かかるため、その間は立ち入りを制限する必要があります。事前に保護者や関係者に伝え、混乱が起きないよう準備を整えておくと安心です。
施工業者を選ぶ際には、学校や公共施設の施工実績があるかどうかもチェックポイントになります。子どもたちの安全に対してどのような配慮ができるか、提案内容からも業者の姿勢が見えてきます。
→ ゴムチップ舗装の学校・施設施工例を見る:https://www.yurikougyou.jp/construction
導入を検討するときに確認すべきこと
ゴムチップ舗装を校庭に取り入れるかどうかを考えるとき、まず検討すべきは「どの場所で、誰が、どのように使うか」という点です。全体を一括で施工するのか、一部だけを改修するのかによって、費用も工程も大きく変わります。目的や使用頻度を明確にすることで、優先順位をつけやすくなります。
あわせて、施工後の維持管理体制についても確認しておきましょう。清掃や点検を誰がどのように行うか、補修が必要になった場合に相談できる業者がいるかどうかも、安心して運用を続けていくうえで大切なポイントです。
検討段階では、費用や耐久性だけでなく、安全性や快適性といった目に見えにくい価値にも目を向けておくと、後悔のない判断につながります。
→ ご相談・お問い合わせはこちら:https://www.yurikougyou.jp/contact